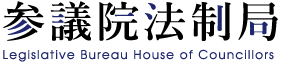変わる女性の資格
我が国には、様々な国家資格がありますが、かつては「女性の資格」として法律上位置付けられていたものがありました。
看護師、准看護師、保健師、保育士及び歯科衛生士です。
このうち、看護師、准看護師及び保健師については、平成13年に参議院の議員立法として提出され、成立した保健婦助産婦看護婦法の一部改正法により改正されるまで、男女で資格の規定方法が異なっていました。
女性が業とする場合には「保健婦、看護婦、准看護婦」と、男性が業とする場合には「保健士、看護士、准看護士」と名称自体が異なっていたほか、これらの資格はもともと女性の資格とされてきたために、男性については法律上特殊な定め方がされていたのです。
すなわち、法律上、看護婦については「―を業とする女子をいう」と規定し、原則として女性が業とする資格として定める一方、男性が看護士として業を行う場合については法律の附則で例外的に規定されるにすぎなかったのです。
保健婦についても、平成5年に男性も「保健士」として業を行うことが認められましたが、これも附則で「保健士の名称を用いて保健指導に従事することを業とする男子については、この法律中保健婦に関する規定を準用する」と定められていました。
このように男性については附則で例外的に定めが置かれるにすぎなかった保健婦(保健士)、看護婦(看護士)及び准看護婦(准看護士)について、男女共同参画の観点から、同一内容の資格については男女同一の名称とすべきとして、平成13年の改正によってこの附則が削除され、男女一本化して「―を業とする者をいう」と定められ、名称についても「保健師、看護師、准看護師」にそれぞれ変更されました。
同様の改正が行われた資格として保育士があります。昭和52年に男性に資格が開放された際には附則で例外的に定めが置かれるにとどまっていたものが、平成10年の児童福祉法施行令の改正における「保母」から「保育士」への改称に伴って附則が削除され、男女で規定が一本化されたのです。
歯科衛生士も同様に男女で異なって規定されていましたが、平成26年に歯科衛生士法が改正され、歯科衛生士の定義における男女の区別がなくなりました。
このように法律上原則女性と定められてきたものが、名実ともに男女共通の資格として規定されるようになってきています。
もちろん、依然として、女性だけに限定される資格もあります。平成13年の改正により「助産婦」から名称が変更された「助産師」です。助産師は、出産という女性特有の事柄にかかわる資格であることから、男性への開放に対しては議論の多いところとなっているようです。
ところで、平成13年の改正では、いずれも「―師」と名称が変更されましたが、資格の名称について「士」と「師」を区別する基準があるのでしょうか。
これについては付け方の基準として明確なものはなく、従来の名称との均衡を考慮して付けられているようですが、一般的に「師」は医療関係、衛生関係など厚生労働省所管のものに多く見られます。平成13年に改正された資格は、いずれも医療・衛生にかかわるものですし、看護士や保健士が男性に対して使われてきたという経緯から、「師」が用いられたものと思われます。
いずれにせよ、資格の名称には、人それぞれの思い入れがあり、平成13年の改正のように、長年定着していた資格の名称を変え、それによって資格の性格も変わる場合には、資格保有者や国民の賛同が得られるものとする必要があります。
平成13年の改正や過去に行われた看護士や保健士導入の法改正が主に議員立法で行われたということは、名称一つをとっても、資格に対する考え方が様々であることを表しているといえるでしょう。
- ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆し、その後適宜のタイミングで改訂を加えておりますが、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。