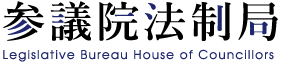負担金について
私たちが日々の生活を営むためにお金が必要であるのと同様に、国や地方公共団体が様々な活動を行う場合にもお金が必要です。それを確保する手段として、租税を思い浮かべる方が多いと思いますが、今回は、租税以外の収入の一つである負担金を紹介します。
負担金とは、特定の公益事業と特別の利害関係を有する者に対し、その事業に必要な経費の全部又は一部を負担させるために課される金銭給付の義務のことをいいます。負担金には、特定の事業より特別の利益を受ける者から徴収する受益者負担金や、特定の事業を必要とさせる原因をつくり出した者から徴収する原因者負担金等があります。
受益者負担金は、公益事業により広く社会的な利便がもたらされることはあるとしても、一般的な利益を超えた特別の利益を享受する者がいる場合、衡平の観点から、その者に費用を負担させるものとされています(道路法61条等)。ただ、制度によっては、具体的な受益者や受益の範囲の把握が困難なため、あまり活用されていないものもあるようです。
原因者負担金は、第三者が道路や港湾等の施設を損傷させた場合、衡平の観点から、それを補修するための費用をその者にも負担させるものとされています(道路法58条等)。不法行為による損害賠償と似ているようにも思えますが、同条と民法709条(不法行為による損害賠償)を見比べると、故意・過失について、前者には言及がなく、後者には言及があるといった違いがあります。
このような負担金は、特定の事業に関し特別の関係にある者から徴収される点で、租税とは区別されています。もっとも、マイカー購入など自動車の取得時に支払う自動車税環境性能割(地方税法145条1号)は、自動車がもたらすCO2排出等の社会的コストにかかる行政需要に着目した原因者負担金的性格を有する税といわれています(総務省ホームページ)。一方、平成30年に創設された地域再生エリアマネジメント負担金制度(地域再生法17条の8)は負担金と整理されており、租税と負担金の区別は相対的なところがあるのかもしれません。
ところで、負担金と法律の根拠は、どのような関係にあるのでしょうか。この点、財政法10条は、国の特定の事務に要する費用を国以外の者に負担させるには、法律に基づかなければならないと定めています。ただし、この規定については、施行日を定める政令(同法附則1条1項参照)が制定されていないため、昭和22年に成立した法律であるにもかかわらず、未施行の条文となっています。理由は諸説あるようですが、今では各法律で負担規定が整備され、その目的はおおむね達成されていると説明する文献もあります。
いろいろな法律を眺めていると、ときどきこのような珍しい規定に出会います。皆さんも、勉強や仕事で法律をひもといてみると、思わぬ発見が待っているかもしれません。
- ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2025年7月に編集・執筆し、その後適宜のタイミングで改訂を加えておりますが、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。